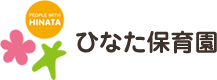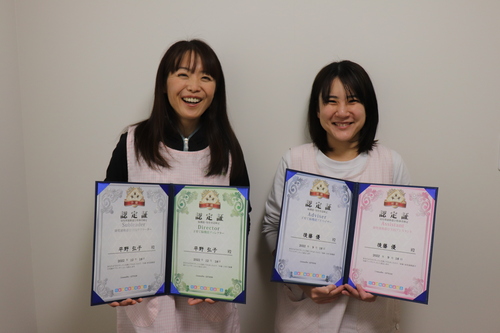食育で食の楽しさを感じる
食は楽しむものです。子どもたちには様々な体験を通じて食の楽しさを感じて欲しいと思います。食を通じて、将来を担う子どもたちに何を教え、伝えるべきか。そんな命題に真摯に向き合い、食育を実践しています。大人になってから、あるいは高齢者になってからではなかなか栄養に対しての行動は変えにくいものです。食習慣は子どもの頃に形成されますので、この時期の意識づけが大事だと考えます。
-
-
農業体験で五感を刺激する
種まき・苗植えから管理・収穫まで、自分たちの手で農作物の世話をすることで、成長を観察する力が身につきます。普段何気なく口にしている野菜がどのように作られているのかがわかります。例えばトマトであれば、種から小さい芽が出て、枝が伸び、緑の実がなって、だんだん赤くなるなど、成長の過程を知ると、食べ物が身近に感じられるようになります。自分で野菜を育てることで好き嫌いがなくなる子どももいます。また畑作業を通じて、土の感触、植物の感触、水の冷たさに触れ、また土の中に虫を見つけるなど自然と触れ合うことで子供たちの感性は刺激されるなど、農業体験は学びの宝庫です。
-
-
-
-
食への感謝の気持ちを育む
自分が育てた野菜を収穫し、丹精込めたお野菜が立派に育つことを経験することで、自然の恵みに感謝の気持ちを持てる子供に育ちます。また、その野菜を使用して厨房で調理してもらうという機会を大事にしています。自分たちが育てた野菜を目の前で調理してもらい、給食やおやつとして食べます。食事の前に「いただきます」と言うことや、残さず食べることなど、食への感謝の気持ちを育みます。
-
-
-
-
調理体験で食に関わる人への思いやりの気持ちを育む
自分が育てた野菜や園庭の木々になる果実を使い、調理体験をします。清潔面に気を付けながら、調理器具の準備から調理、試食、片付けまで全ての工程に関わります。自然の味や香り、調理、成型、盛り付けなどを体験し、食べるという楽しみ、そしていつも料理をしてくれる人たちへの思いやりの気持ちを育みます。
-
-
-
-
八百屋さんごっこで流通の流れを知る
隣接する高齢者デイサービスの利用者様との八百屋さんごっこを通して、自分で収穫した野菜を売る遊びをします。保護者様にもおもちゃのお金で販売します。こうして、「農家の方が野菜を作る⇒それがお店で売られる⇒それをおうちの人が買う⇒おうちの人が料理する⇒家族一緒に食べる」という流通の流れも学びます。
-
-
-
-
管理栄養士からの講座で知識と食を選択する力を養う
単に栄養成分を知るのではなく、食べ物がどのように作られ、体の中でどのように利用されるのか、保育者と一緒に深く学びます。例えば、白米の糖質が体力を与えてくれる、野菜のビタミンが体の抵抗力を高めるなどです。
また、例えば「カルシウムが必要な時期には牛乳や乳製品を選ぶ」というように、自分の健康状態や生活習慣に合わせ、適切な食品を選ぶことが出来る力を身につけます。
管理栄養士の先生がイラストを用いてわかりやすく伝えてくれるので、子どもたちは興味津々で楽しく学ぶことが出来るのです。 -
-
-
-
「解体ショー」で食べることを考える
隣接する高齢者施設「デイサービスひなた」で毎年行われるマグロの解体ショーを見学に行きます。子ども達の目の前で70キロ級の巨大マグロがさばかれ、「魚さんも小さな魚さんを食べて大きくなるんだよ」「内臓や血があって、それは私たちにもあるんだよ。」「この魚の命を頂いているから、残さず食べようね。美味しいと食べたら、魚さんは喜んでくれるんだよ」と伝えます。
-
-
面白いからまたやりたくなる運動遊び
生涯にわたって体を動かすことを楽しみ、健康を維持するためには、乳幼児期に楽しく、繰り返したくさんの体の動を体験することが必要です。大切なのは、やらされたり強制されたりするのではなく、子ども自身が面白いと感じ、楽しく経験できることです。子どもたちのワクワク感をいかに刺激するか考え、環境を整えることを大事にしています。
-
-
幼児期に身につけたい36の動きを全て獲得できる園舎・園庭設計
身体教育学・発育発達学を専門に子どもの体力について長年研究をされている山梨大学の中村和彦教授が推奨する「幼児期に身につけたい36の動き」を全て獲得できるよう、園舎内・園庭を設計しました。楽しさにつられて自然と動く仕掛けがひなた保育園にはあります。
-
-
-
-
運動保育士が在籍!脳の神経に働きかける運動遊び
0-1歳児にはバランス感覚を養う遊びや手足の協調運動を高める簡単な体操を取り入れた遊びを提供します。また、2歳児になると、リズム運動やチームプレイを通じて社会性や身体の柔軟性を促進します。跳び箱、鉄棒、平均台、バランスストーン、縄跳び、フラフープなど、様々な運動器具を用いて楽しみながら運動遊びを行います。
子どもたちが「面白そう」「やってみたい」と感じ、体を動かす楽しさに気づけるように導く為、運動保育士・保育者自身が楽しむことを大事にしています。
-
-
-
-
スイミングコーチとしても活躍する保育士が在籍!楽しいプール遊び
毎年7月~9月まで、広場に4.5m×2.2mのプールを設置します。スイミングコーチの企画した内容で、年齢に合わせた遊びを通して全身運動を水中でしてもらいます。水深80cmのプールで浮き輪をつけて浮くところから、顔つけ、もぐるなど、遊びを通して子供たちはいつの間にか出来るようになります。
-
-
自然体験
四季折々の植栽や果樹に囲まれ、花の色(視覚)や香り(嗅覚)、葉擦れの音(聴覚)や葉の触感(触覚)、美味しい果実(味覚)を楽しめます。園庭には、中高木・低木・かん木・草花と、様々な種類、様々な高さの植物を植えています。お日様の温かさ、日陰のひんやり感、風が頬を触れていく感触。草木が風に揺れる様や香り。
自然体験では、自然への愛着、観察する力、自然や友達への配慮、意見交換しながらお友達と何かを達成する力など、生きるための基礎力が養われます。
-
-
五感をフルに使う自然との触れあい
ひなた保育園の園庭にはたくさんの虫や鳥が遊びに来ます。「かわいい」「怖い」「面白い」「触ってみたい」と、様々な感情を持ちながら生き物に関心を持つ子どもたちの姿があります。目の前のものをよく観察して触ったり、耳を澄まして鳥や虫の声を聴いてみたり、石ころや葉っぱを集めて並べてみたり、おのずと五感をたくさん使って遊ぶことが出来ます。中には採集した虫を虫かごで育てていても、死んでしまい土に埋めることもあります。この経験は命の大切さについて考える貴重なきっかけとなります。
-
-
-
-
五感を育む砂場での体験
子どもたちは砂場で色々なものを作って遊びながら想像力を働かせます。砂で水を含ませて泥を作り、お団子を作るなど、イメージを膨らませながら創造する力を育みます。砂や水分を含ませて作る土など、感触を手足の感覚で自然に確かめながら感性を育みます。作りたいものに合わせて混ぜる水の量を調節し、バケツに水を入れて運ぶ時にどの程度入れると運べなくなる程重くなるのかなど、砂遊びの結果から色々学ぶことが出来ます。根気強く作品を作る集中力や工夫して遊びを発展させる思考や、子ども同士の道具の貸し借りから社会性を学ぶことが出来ます。保育者も裸足で砂遊びをするなど、「気持ちいい!!」と言いながら子供たちと一緒に大はしゃぎしています。
-
-
-
-
保育者の想い
私達保育者は、安全面に気を配りつつ、子どもたちが自由に遊べるように見守ることを徹底しています。また保育者が「遊び方を教える」のではなく、子どもが何かを発見する機会や自ら考えたことを試す経験を大切にしています。子ども達が「やってみたい」と思ったことはどんどんやってもらいます。保育者に見守られながらチャレンジできる環境を整え、安心感の中で積極的に行動することが出来るようサポートしています。
-
-
お手伝い活動
-
-
テーブル拭きや給食の配膳、食器運び、午睡マットの片付け、小さい子のお世話など、お手伝い活動を取り入れています。子どもたちの主体性を尊重し、「やってみたい」という意欲を育みます。完璧に出来なくても、やったことを承認し、「ありがとう」という言葉をかけると、人の役に立ったことの喜びと達成感、そして自己肯定感が生まれます。また、お手伝いの最中に難しさを感じた時は、「どうしたらいいかな?」など創意工夫する力も育ちます。
-
-
お当番活動
-
-
朝の会の連絡事項発表やお天気調べ、金魚のえさやりなど、お当番活動を取り入れています。自分の役割を認識して、自信を持って行動するなど責任感が生まれます。友達と一緒にやる場合は、同じ目的に向かって協力する充実感が育まれます。また「少し疲れたな」と思っても、責任を持って最後まで取り組むことで、物事をやり抜く力が育ちます。
-
-
高齢者との関り
-
-
隣接する高齢者施設「デイサービスひなた」の利用者様との関りを大切にしています。デイサービスでのイベントに参加したり、保育園内の畑で一緒に野菜の水やりや収穫をしたりと、様々な交流の機会を設けています。最初は緊張気味の子どもたちも、自分たちに向けられた愛情いっぱいの眼差しに次第に安心感を持ち、笑顔いっぱいの姿を見せてくれるようになります。「周囲の人々からたくさんの愛情を受けて、温かく見守られている」ということを子どもたちに感じて欲しい、そして多様な人に対する信頼感を持って、自分に自信をつけ、お年寄りを優しく労わる思いやりの気持ちを育んで欲しいと思います。
-
-
生き物との関り
-
-
ひなた保育園では、金魚やカブトムシの飼育をしています。飼育に関わる作業(餌やり、掃除など)をお当番制で子どもたちの役割にし、役割認識を持てるようにしています。身近な生き物と触れ合うことで、自然・命への考えを深め、命あるものへの労わり、大切にする気持ちを持って関わる心が育まれます。成長する様子を間近で観察し、生き物が寿命を迎える時には命には終わりがあることを学びます。「土に埋めてあげる?」「どこが良いかな?」「隣にお花を置いてあげたい」など様々な感情をもつ体験にもなります。
-
-
地域との関り
-
-
ひなた保育園は、広く地域に開かれた存在でありたいと思っています。お野菜やお肉、お魚を納めて下さる業者の方々や、ご近所の皆さん。隣接する高齢者施設「デイサービスひなた」、だんじりや夏祭りでお世話になる自治会の方々など。幼少期に親以外の大人とどれだけ多く、どれだけ深く関われたかということは、子どもの人生に大きな影響を与えます。地域の皆さんと、様々な角度から日常的に交流をすることで、より充実した園生活を送ることが出来ると思います。
-
-
保護者様へのプラスαの寄り添い
-
-
母乳を卒業出来ていなくても大丈夫
冷凍母乳の対応もさせて頂いております。(搾乳後速やかに冷凍し、冷凍後1週間以内のものを原則とします。)入園前に手順についての説明と、哺乳瓶を嫌がったり、母乳の微妙な温度の違いで飲まなかったりした時の対応についてなどきちんと事前に打ち合わせを行いますので、ご安心ください。
「母乳を卒業できないから保育園に預けられない」という心配はありません。卒乳するまでの期間、保育園にタイミングに合わせてお越し頂き、授乳を保育園でして頂けるよう、スペースを設けています。お気軽に相談して頂けます。
-
-
-
-
ほっと一息。リフレッシュ制度
ひなた保育園では、保護者の方々がご自身のことと子育て、仕事など両立して頂けるよう、お仕事がお休みの日でも保育園に預けて頂ける「リフレッシュ制度」を取り入れています。「美容院に行きたい」「夫婦でゆっくりランチしに出掛けたい」「家でのんびりリラックスしたい」など保護者様のリフレッシュを応援します。「保護者様がhappyで心にゆとりがあれば、子どももhappy!」そういう考えから生まれた制度です。
-
-
-
-
登降園時はストレスフリー。安心のサポート
保護者様の中には、ご兄弟で預けて下さっている方、双子で預けて下さっている方、妊婦の方、第二子を出産直後の方など様々おられます。そのような方々からは「到着して車から二人の子を同時に抱っこして連れて行くのが大変です」「出産したばかりの下の子を車に乗せたまま園内に連れて行くのは不安です」「雨の時は駐車場から園内まで傘をさせないので大変です」などの相談を頂きます。そうした場合には、保育者が駐車場の車の所まで迎えに伺い必要に応じたサポートをさせて頂いておりますので、ご安心してストレスフリーで登降園して頂けます。
-
-